8-8.仕事の幅の広げ方
世間ではスペシャリストが必要とされているとか、ゼネラリストはもう時代遅れだとかキャリアのパターンについて、さまざまな意見が飛び交っています。また社内でキャリアへの希望を聞くと、結構な確率でキャリアの幅を広げたいのでほかの職種を経験したい、という方がいます。
キャリアは人それぞれであり、また綿密に計画したからといって、そのとおりになるわけでもないのですが、実態をしっかりと踏まえたうえで考えるということは大切なことですので、わが国の状況を見てみましょう。
少々古いデータにはなるのですが、連合総研が1995年に実施した「新しい働き方に関する個人調査」によると、企業内キャリアを見ると、仕事の幅が特定の職能分野のなかに収まる者が多いという結果になりました。
つまり、社員の企業内におけるキャリア形成のあり方は、従来いわれているような、多様な職能分野を経験させるものではなく、特定の職能分野内で行われています。社員のキャリア形成のあり方から判断すると、職業能力はゼネラリストと呼べるものではなく、スペシャリストがあてはまるといえる、と結論づけています。
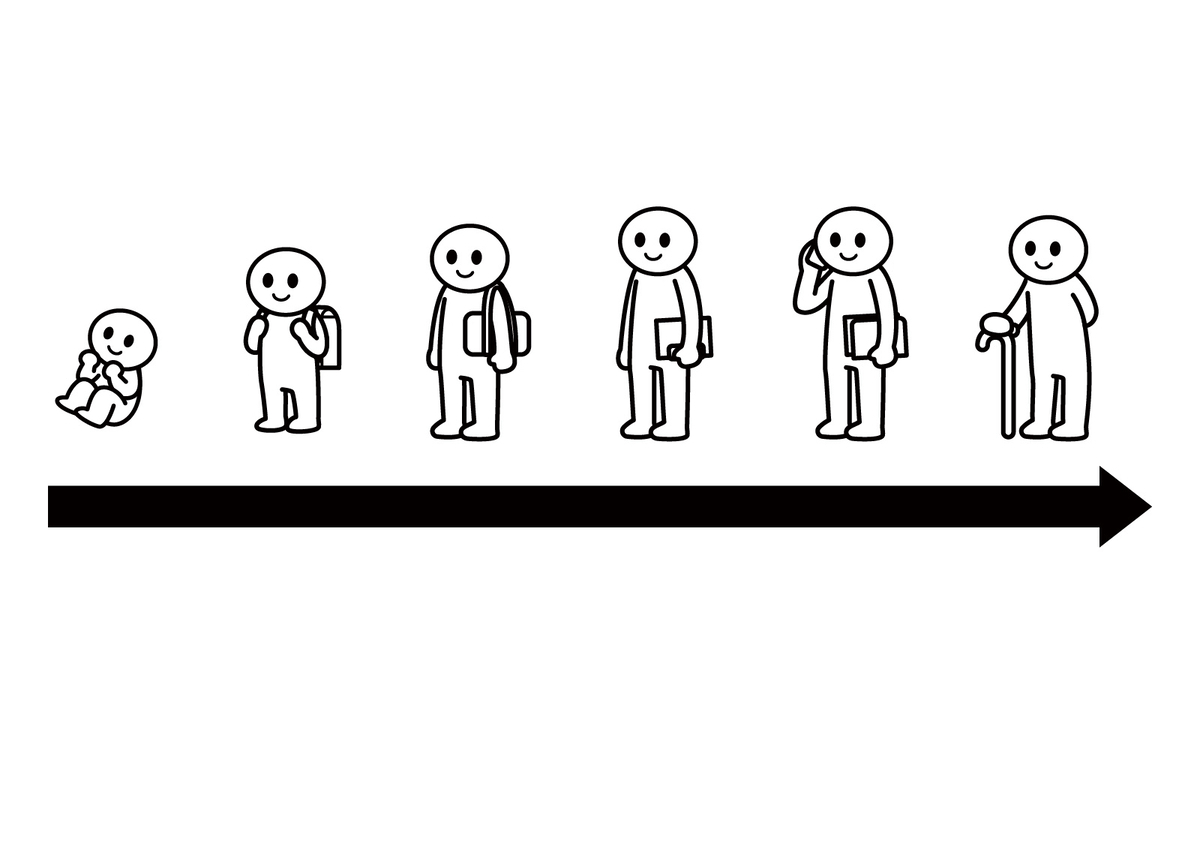
専門性の獲得という観点から考えても、専門性を獲得する時期は、企業内のキャリアから見ると20代後半から30代前半という働き盛りという時期であり、この時期の仕事を通じて獲得されることが多いと思われます。
この10年程度の時期に複数の職種を経験するということは現実的ではなく、また経験した場合には、異動後の職種ではまたゼロからの専門性構築ということに なるので、異動しなかった場合と比較すると優位性があるとはいいにくいと思います。
まったく違った職種へチャレンジしてみる、というのであれば、20代の早いうちに異動することをおススメします。また自分はこの分野の専門性を軸にしていこうと決めたならば、その職種内、たとえば経理であれば、財務会計、管理会計、税務会計といったように同じ職種のなかで、分野をまたいで経験を積むことをおススメします。同じ経理といっても職種が違うくらい仕事中身も必要な知識も変わってきますので、この3つの領域をマスターするだけでもかなりのストレッチだと思います。
これからの変化の激しい世の中で、付加価値をどのように創造していくのか、という観点でご自身のキャリアを考えてみてはいかがでしょうか。